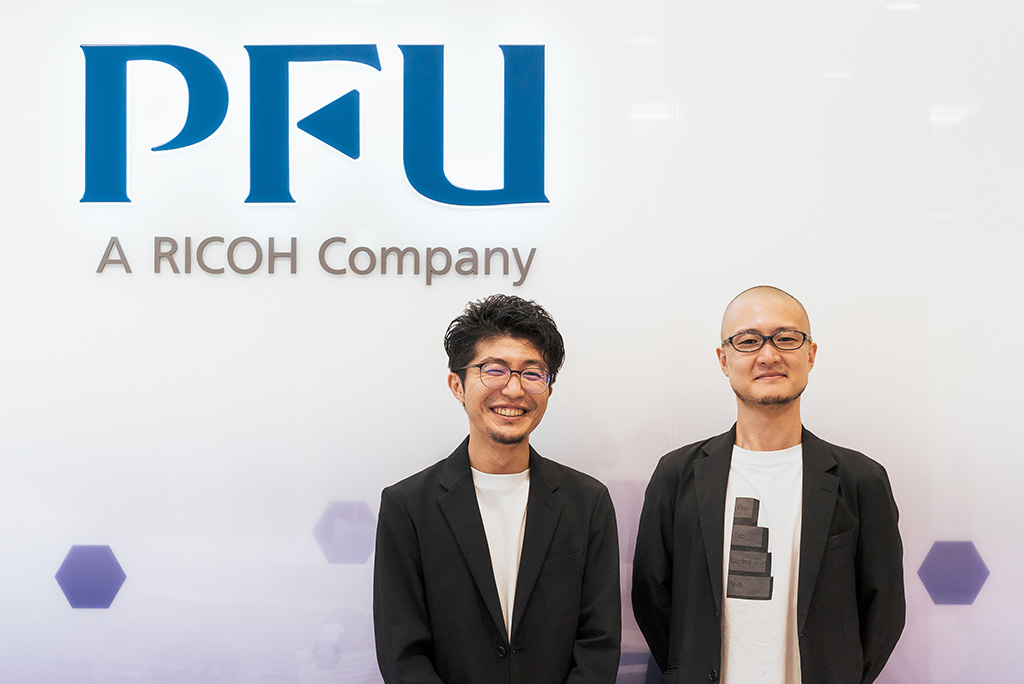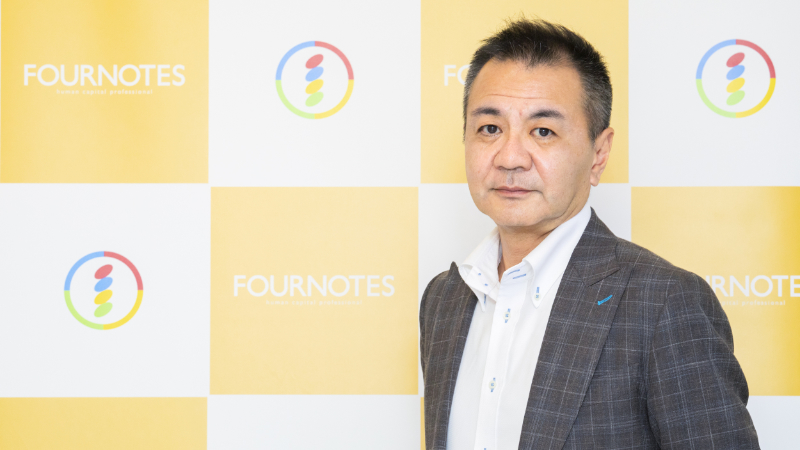上場企業の事業承継、その舞台裏に迫る! 〜アイザワ証券新社長・藍澤卓弥氏が、事業承継の先に見出す新戦略とは?

社会全体が高齢化する中、多くの中小企業でも経営者の高齢化が進み、後継者不足による廃業が大きな課題となっています。しかも廃業予定企業の4割以上が、今後10年間の将来性について「現状維持は可能」と答えていることからもわかるように、中小企業が事業を引き継がないことによる社会の損失は決して少なくありません(2016年2月 日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインターネット調査」)。
こうした待ったなしの状況にある「事業承継」の問題について早めに対策を打つことは、事業を長く続けるためのカギとなります。特に、多様なステークホルダーが絡む上場企業の事業承継に目を向けることは、経営に携わる者にとって、大きな意味を持つはず。
2018年7月、創業100周年を迎えた上場企業・アイザワ証券(藍澤證券株式会社)が事業承継を実施しました。同社は事業継承に向けてどのような経緯をたどり、何を準備したのか。また新たに打ち出した経営方針や、2つの「X-D(経験デザイン)」施策とはどのようなものか。新社長・藍澤卓弥氏に聞きました。
上場企業を引き継ぐとはどういう体験か?

―藍澤社長は、お父様である藍澤基彌氏(現・会長)から会社を引き継いだわけですが、ご自身としては、いつ頃から“継ぐこと”を意識していたのでしょう?
私は大学を卒業してから31歳でアイザワに入社するまで、野村総合研究所でSE(システムエンジニア)をしていたのですが、それまで全く会社を継ぐことを意識していませんでした。アイザワに戻ったきっかけは、ちょうど会社が上場する直前に父から「上場したらプライベートカンパニーではなく、パブリックカンパニーになる。そうなるとオーナー社長であっても自分の息子を簡単に会社に入れられなくなる。戻るなら今だ」と言われたことです。いろいろ悩みましたが、最終的には金融業に携わりたいという思いからアイザワに入社することを決めました。
ただそのときも、SE時代に金融業界のシステム構築に携わった経験から、純粋に金融業を生業にしたいと思ったからで、その時点では事業承継を意識していませんでした。入社し、専務になったところで、当社が日本アジア証券を合併することになりました。その際、デッドラインの3日前に父から突然「社長として行ってこい」と。さらに就任前日に「これからは社長と社長という対等な立場になるのだから、思う存分、好きなようにやってみろ」と言われまして。そこで初めて“将来、アイザワ証券の社長になる”ということを本格的に意識しました。
―日本アジア証券を統合していく一番難しい時期でもあったと思うのですが…。
そうですね。それもあって、父からは「毎朝、必ず報告をしろ」と。父とは家が近いので、父が毎朝家の前で私をピックアップし、車中で報告会を行いました。予算対比でどれくらい利益が出ているのか、問題が起きていないかなど、時間は40分、50分ほどでしょうか。私が日本アジア証券の社長をしている際に、個別タスクの中で一番時間を使ったのは、この報告会かもしれません。今にして思えば、このときの報告会が父の巧みな事業承継のひとつだったのかもしれませんね。
―グループ会社の社長として難しい合併の過程を見ていったわけですが、いよいよ本社の事業を引き継ぐという話が出たのはいつ頃だったのしょう?
新社長に就任したのが2018年7月で、その4ヶ月前。父から突然「墓参りに行こう」と電話が来まして。どういう風の吹きまわしだなんて思いながら車を出して父を乗せて向かっていたら、突然父が「7月から社長をやれ」と。いずれ社長になるという意識はあったのですが、そう言われた時はびっくりして、思わず事故りそうになりました(笑)。
というのも、実は昨年の7月というのが、まさに日本アジア証券の合併の期日だったからです。それに加えて会社が創業100周年を迎えるときで、イベントも目白押しでしたから、そんな中で「新社長誕生」となると混乱が増すだけだろうと思ったのです。
ただ、昨年から今年にかけて証券会社各社で事業承継ブームが起きていて、当社以外にも中堅の有名どころが軒並み社長を交代しているんですね。父がその流れに感化された一面もあったかもしれません。
新体制で打ち出した「人」重視のマネジメント手法

―社長就任や合併で体制が大きく変わったかと思います。その際の内部統制の在り方について、何か準備をしていたことや、対応で難しかったことがあれば教えてください。
内部統制については、コンプライアンスを含めた基本的なルールは、アイザワ証券側に合わせています。ですから、会社の内部統制そのものは大きく変えてはいません。
問題は合併ですね。日本アジア証券の社員からすると、これまでのやり方が変わりますので、当然戸惑いがあるわけです。そこで合併半年前から、合併準備委員会を立ち上げ、両社で議論を重ねてきました。アイザワはこういうやり方、日本アジア証券はこういうやり方をしていると、互いの違いを認識したうえで、どうすれば円滑に寄せていけるかアイデアを出し合ったんです。
その結果、例えば、アイザワの社員が日本アジア証券に出向して教えながら一緒に仕事をする、あるいは逆に日本アジア証券の社員がアイザワに来て一緒に働いてもらうなどの取り組みを進めてきました。
―経営方針やマネジメント手法について変革したことはあるのでしょうか。
一般的に上場企業の経営というのは組織的に行うもので、非上場の企業はいわゆるワンマン経営というイメージがあるのではないでしょうか。当社の場合は、上場はしているけれど、前社長がオーナー経営者としてワンマン経営を続けてきたという経緯があります。ワンマン経営には良い点も悪い点もありますが、合併で1000人規模に膨れ上がった会社において、従来型のやり方そのままでは通用しないというのが、前社長も含めた我々の共通認識でした。そこで私の就任後に打ち出したのが、トップマネジメントチームを軸としたチーム経営制です。
これは現代経営学の生みの親と呼ばれるピーター・ドラッカーが提唱するマネジメント手法をベースにしたものです。ドラッカー氏は、トップマネジメントを一人の人間が独占するのではなく、複数の人間によって分担する必要があると説いています。当社でも、マーケティングやイノベーションなど8つの領域に対してそれぞれ担当役員を決め、それぞれが企画・立案・実行までを責任を持って遂行していくトップマネジメントチームの体制を構築していくことを決めました。
体制を変更した背景には、時代の変化もあります。非常に振れ幅が大きくなり、相場や経済の動きの見通しがきかない。いわば明日をも知れぬ状況で、お客様の価値観も大きく変わってきています。こういう状況のときには、お客様は儲けるよりも資産を守る方に比重を置きはじめます。となると、我々自身も新しい証券会社のあり方を模索しなければいけない。そのためにはやはり「人」が変わらなければいけません。
―「人」とはつまり、顧客と向き合う社員自身が変わらなければならないと。
はい。変わるためには、やはり育成の方法を根本から見直さないといけません。そこで我々は、社員に主体的にキャリアプランを決めデザインしてもらう「CDP(Career Development Program:キャリア・ディベロップメント・プログラム)」も導入しました。
従来のように会社が「君はこういうスキルを持つ人間になりなさい」と、社員にお仕着せのキャリアプランを強いていては、変化が早い社会の中では、せっかく身につけた経験やスキルが陳腐化することも考えられます。我々は社員に、お客様が何を求めているのかを自分で考え、その実現のために何が必要なのかを自分自身で考え、実行してもらおうと考えています。
具体的には、会社からは社員に向けて彼らが目標とできるロールモデルをどんどん提供します。さらに、そのロールモデルに少しでも近づくためには、会社のどんなリソースを活用すればよいのか、誰に相談すればいいのかなどのヒントもどんどん提供する。でも、その中から何を選ぶかは社員自身、という仕組みを構築していきます。
これは、従来言われている「CDP」と比べ、より社員の思いを実現しようとする比重の方が大きいものだと思います。社員自身がキャリアプランのオーナーになり、自らアクションプランを立て実行する。要するに社員に、自分のキャリアの執行責任者になってもらうわけですね。
この「CDP」の導入により、部下のキャリアのロードマップに寄り添う現場の上司や、各社員のキャリアを管理する人事部には大きな負担がかかることになります。そこで今、人事部の人員を増やすとともに、人事部長にエース級の人間を据えるなどの調整を進めています。さらに人材育成を本気で進めていくことを示すため、「CHO(Chief Human Officer:最高人事責任者)」の役職を設け、私自身が兼任することにしました。
顧客と社員、双方の幸福実現をつなぐ2つの「X-D」

―従業員が自分でキャリアプランを考え実行できるシステムというのは、従業員育成において非常に参考になる仕組みですね。ところで御社はこれまで、顧客に希望や安心を提供することにこだわる「超リテール証券」という営業コンセプトを掲げていました。この方針に変更はなかったのでしょうか?
現在でも、従来の証券業務の在り方を超え、お客様に心から信頼される証券会社になるという「超リテール證券」を目指す方針に変更はありません。人生100年時代となった今だからこそ、お客様の人生に寄り添い、お客様の資産形成をソリューションスタイルでサポートすることの必要性を強く感じています。
ただし、お客様の人生に寄り添うための道筋には大きな変更があります。すでにお伝えした「人」の育成にも絡むのですが、我々は「CX-D(Customer Experience Design:お客様の体験をデザインする)」と「EX-D(Employee Experience Design:社員の経歴をデザインする)」という2つの「X-D」を軸にした新たなコンセプトを打ち出しました。
―2つはそれぞれどういった内容のものでしょう?
まず「CX-D」とは、お客様の体験や経験をデザインするという概念です。「モノよりコト」という言葉があるように、今はお客様に物を販売する時代ではなく、事を売る時代でしょう。金融商品も単品で売る時代でもないし、そういうニーズも薄い。
そこで我々は、単品セールスではなく、我々の金融商品や提携企業の商品を絡めたお客様の生活スタイルそのものを提案していこうと考えています。例えば、30代後半、管理職になったばかりの女性には、健康維持のためのエクササイズを週に3回しながら、投資も進め、投資で得た利益でプライベートを充実させるための旅行も楽しんでもらう。こうしたお客様の体験をデザインし提案することで、これまで以上にお客様に喜んでいただき、安心をお届けできる証券会社になろうというのが「CX-D」の狙いです。
一方、こうした提案型のやり方を取り入れていくときには、ひとえにその体験が良いものであると営業マン自身が信じられるかどうかが重要です。
今後は、社員自身にも自らのキャリアをデザインしてもらおうと考えています。誰かに指示されたものではなく、自分自身でキャリア全体をデザインすることの素晴らしさを体験してもらおうと。生活をデザインすることの良さを信念として持つ社員が、お客様の生活スタイルもデザインし提案することが、力強い営業につながると思うのです。この、社員が自身のキャリアをデザインすることを「EX-D」と呼んでいます。先述した「CDP」も、これを実現する手段のひとつですね。

―顧客向けに打ち出す「CX-D」というと、従業員向けの「EX-D」が対になり、営業力強化と幸福追求につながっていくところが興味深いですね。この取り組みはすでに動き出しているのでしょうか?
もちろんスタートしています。さらに、これからより加速度的に進めていこうという段階です。社員にいろいろな経験を提供するということから言うと、すでに社外との積極的な提携戦略(提携金融機関との人材交流/同待遇転籍制度)を進めています。
これは、地域の金融機関と提携し、同じ待遇を保証しながら当社の人材を送り出したり、逆に他から受け入れたりする取り組みです。例えば、山口県にある株式会社西京銀行や岡山県の笠岡信用組合、東京の第一勧業信用組合との間では社員の転籍がいくつも実現していて、その中で当社の社員が普段の業務では得られないような視点、スキル、人的ネットワークを獲得していますし、提携先の金融機関にも喜ばれています。
また、静岡大学ではアイザワゼミを運営していますが、当社の若手社員も数名送り出しました。このゼミは文部科学省のプロジェクトに関わるもので、アントレプレナー(起業家)を育てることをテーマにしたもの。大学での学びに感化された社員が、当社の中に企業内起業に関する勉強会を立ち上げるなど、新たな動きにつながった事例もあります。
こうした社外での経験は、社員の「EX-D」を深めるものだと思います。この観点でも、今後さらにこのような提携戦略をより体系的に進めていく考えです。
―今後、社会の変化に伴って証券業界も激変していくと思います。その中での生き残り戦略という視点で事業承継を捉えたときに、御社ではどのようなことを行っていこうとしているのか教えてください。
「超リテール証券」を含め、今回お伝えしたことは全て我々が目指すゴールですが、口先だけでそれが実現できなかったら全く意味がありません。そしてこれらが実現できるかどうかを突き詰めて考えていくと、やはり「人」が全てだと思います。私自身がCHOの立場を兼ねているので、なおさらそう感じます。
社員一人一人が時代の変化に合わせて変わっていけるかどうか。何が正しくて、どんな行動を起こすべきかを決められる人間を育てていけるかどうか。それこそがこれからの変化の時代を生き残るための我々の戦略のベースにあることだと思います。
この軸は絶対にぶらさない。ここに向けて突き進んでいくのですが、実現できるかどうかは「CX-D」「EX-D」にかかっていると考えています。
―上場企業にかぎらず、これからの事業承継の形は、新しい経営者が時流にフィットした経営のビジョンを描けるかどうか、そして全てのステークホルダーの幸福をいかに追求するか、この2点がカギになりそうですね。ありがとうございました。

【プロフィール】
藍澤 卓弥(あいざわ たくや)
1974年、東京都生まれ。1997年に慶應義塾大学を卒業した後、株式会社野村総合研究所に入社。2005年、藍澤證券株式会社に入社。2012年、取締役に就任後、2014年に専務取締役管理本部長、2017年に日本アジア証券株式会社の社長に就任。2018年7月、藍澤證券社長、COO兼CHOに就任し、現在に至る。