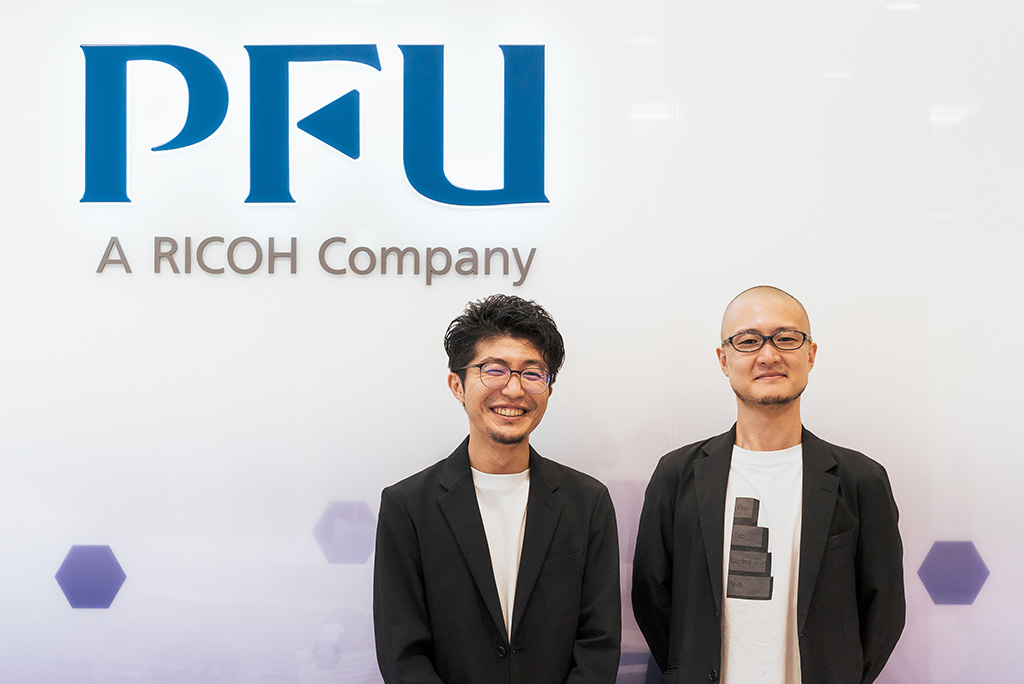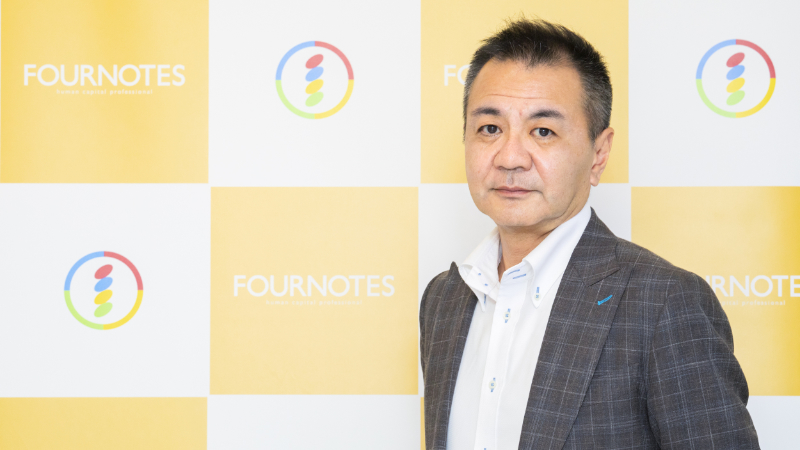AI(人工知能)をサービスのコアにすることによって、労働集約型だったコンサルティング会社がどのように変貌を遂げたか?

社名は「WACUL=ワカル」と読む。「わかる!」という「データの理解」や「共感」、「和」の「カルチャー」という意味も込められている。デジタル・マーケティングの分野で、AIがWebサイトの分析をする「AIアナリスト」で、画期的なコスト削減を実現した。
創業メンバーとしてジョインした大淵氏は、現在は代表取締役CEOとして社を牽引する。なぜAIを使ったサービスをリリースしたのか?成長期の会社ではどのようなマネジメントを実施しているのか?その経営的視線をうかがった。
人の手によるコンサルティングからAI型サービスへの転換
―現在、AIを主軸としたサービスを提供している理由を教えてください。
デジタル・マーケティング(以下マーケティング)の世界は参入障壁が低く、多くのサービスが乱立している状況です。私たちが提供するようなAIを用いたサービスも増え続けています。その他にも企業のマーケティング活動を支援するツールは数多く、さらに1つの企業が複数のツールやサービスを同時に導入するケースもあります。その結果、逆にあまりにもやることが多くなって「1日いろんなサービスの方と連絡していたら終わってしまった」など本質的な改善活動に取り組めないままに疲弊してしまう担当者の方が多数いらっしゃいます。
たとえば、Aというツールで収集しているデータを取りまとめてBというツールで解析して、レポートを作成して関係部署と共有して、PDCAを回しつつツール全体の管理もするなど……
そんな環境の中で、私たちの「AIアナリスト」というツールでは、このような膨大な課題を機械的に、かつ正確に解決していく手段として、AIという技術を用いてきました。特に私たちの「AIアナリスト」は、ワンストップを実現するために、企業のマーケティングに必要なデータを大量に集めて分析して、そこから生まれた集合知をもとに、その企業がどのようにマーケティング活動を行うべきかの方針を立てるまでをAIによって解決しています。つまり、他社のように「分析を行うAI」ではなく、「コンサルティングを行うAI」を作っているのです。
しかし、まだまだクライアントのマーケティング担当者様が自ら手を動かさなくてはならない課題が多く、それらを1つずつでも機械化して、将来的にはマーケティングだけではなく、ビジネスの課題をワンストップで解決できるパートナーになりたいと考えています。
AIの活用はあくまで目的ではなく手段として、いかにクライアントの課題を解決するかということにフォーカスしてサービスを提供していきたいと思います。そこにAIの高度な研究・開発が絡んでくる形が会社としては理想です。
―クライアントに提供するサービスをAIに任せてしまうことに抵抗はありませんか?
ありませんね。人とAIや機械、それぞれは得意なことにフォーカスすべきだという信念があるからです。当社は、かつて「CVを〇〇倍にします」(※)など、成果にコミットするスタイルのコンサルティングを提供をしていました。この成果は、低く見積もればなかなか営業時に案件が取れませんし、高く見積もれば契約こそたくさん取れますが、成果が出せずに返金することになり、結局は自分たちの首を締める可能性がありました。
成果が出せるかどうかの際どいラインで目標設定をし、後は私たちのコンサルティングによって、成果を出すということを繰り返していて、どうにか返金を行うことはなかったわけですが、その取り組みの中で次第にどの程度コミットすればいいのかを見極める精度が高まってきました。このような私たちの経験をもとに、東京大学の松尾研究室との共同研究などを行うなどしてAIに関する知識も吸収し、データの分析と改善方針の立案、そしてその改善幅の予測を行うAIができたのです。
人がコンサルティングしていたときの細かな施策の成功率は、あくまでも正確に測定した数値ではありませんが50パーセント程度だったと思います。それが、AIを使ったサービスとして提供し始めた結果、現在は75パーセントまでに上がっています。75%までいけば、PDCAを繰り返すことで「ほぼ間違いなく」成果が出せると言えるのではないでしょうか。これだけ成果が出ると、AIに任せない理由はありません。
(※)CV:Conversion(コンバージョン)の略称となり、Webサイトの最終的な成果のこと。商品販売サイトであれば商品が売れることなど、サイトを作った目的が達成された状態を指す。
―AI型サービスへの転換によって、成果以外のメリットはありましたか?
クライアントにサービスを提供するために必要なデータを分析するわけですが、その時間がケタ違いに短くなりました。この分析の作業は従来より人の手で行ってきたのですが、2週間程度の時間を要するのがあたり前でした。それがAIではたったの数分程度で済んでしまいます。この分析の作業を縮めることによって、よりリアルタイムなデータを取り扱うこともできるようになり、分析の精度が高まりました。
さらに私たちの作業時間の圧縮によって、コストを大幅に削減させ、販売価格を下げることができたこともあり、おかげさまで「AIアナリスト」は2万8,000件サイトにも使っていただいています。同じロジックで通用しますし、ゆくゆくは海外にも広げていきたいと考えています。
集めたノウハウをオープン化する理由

―「より多くの人にサービスを使っていただく」ことが、会社のミッションと捉えてもよろしいですか?
もちろんそれはそうですが、自分たちのサービスの押しつけになってはいけません。より広範なミッションとして、当社には「知を創集し、道具にする」というものがあります。世界に散らばっている「知」を集め、それらをひとつの体系にまとめて誰にでも使える道具へと変えます。そして、すべての企業や人に開放したいと考えています。
―せっかく作ったノウハウを開放してしまうということですか? 本来は、それを独占的に使って利益を上げるのが一般的なビジネスだと思うのですが…
知識やノウハウというのは、いつかは陳腐化してしまうものです。時代の流れは速いですから、それらを後生大事に抱えていても、すぐに通用しなくなってしまうでしょう。
Webの世界はもともと「オープンであるべき」というカルチャーがあると思っていて、僕もそれを信じています。一番わかり易いのは「オープンソース」という概念ですよね。これはソフトウェアのプログラムを公開して、誰でも使用でき、必要があれば改変できるようにするというもので、多くの人が活用することによって、そのソフトウェアが進化することを目指しています。そのベースとなるのは、「共有」と「利益」を両立させるという考え方だと思います。
私たちも、ツールとして知見をオープンにすることによって、より多くの人に活用してもらい、より多くのデータを私たちに預けていただくことで、私たちのAIがさらに賢くなり、またみなさんに対してよりよい改善提案ができるようになる。こうして、知を集め、また社会に還元し、さらにそれが多くの知を集めることにつながるというサイクルをどんどん回すことで、社会全体が成長することのほうがメリットがあると考えています。
短期的な利益だけを目指すのではなく、長期的な視点に立ったほうがいいですよね。
仲間への任せ方、自分の信じ方

―1年ほど前に代表取締役を引き継がれましたが、迷いはありませんでしたか?
もちろん悩みましたよ。それまでのNo.2という立場からトップになるわけですし。ただ会社としては創業の0から1を生み出す力から、1を10にする力を必要としているフェーズでしたし、自分でやったほうが良いのかな、と思うところもありました。
かなりのプレッシャーはありましたが、結局は周りからの応援もあって、やることにしました。
そういう意味では起業からここまで、本当にタイミングごとに仲間に恵まれています。よく「企業のトップは孤独」という言葉を聞くことがありますが、私に限ってはそんなことはありません。自分だけでできることは限られてますし、任せられる仲間がいて幸せですね。
―仲間を見つけるのはそんなに簡単ではないと思うのですが?
私は、「仲間を探している」ことを事あるごとに表明してきました。すると、みなさん覚えていてくれて、「こんな人材がいますよ」とか「○○ができる□□さんという方が…」など、紹介してくれるんですね。
特に、それを対面で伝えていました。今は手軽にFacebookやtwitterなどのツールで連絡も取れますが、やはり直接会って話すことで相手の印象にも残りますし、自分の「熱」みたいなものを伝えることができると思います。
―自分のビジネスに邁進しようとしている人にメッセージをいただけますか?
仲間に任せることと同時に「自分を信じる」ことを忘れないでいてほしいと思います。会社をやっていると、どうしても外部からあれこれ言われるし、結果もついてこない瞬間もあるし「ブレる」ときってあると思うんですよ。でもそうやってブレたときにした意思決定って、大抵うまくいかないんですよね。なので、自分の感覚みたいなものは最後の最後まで信じるべきだと思っています。
もちろん、私は決定に至るまでには、徹底的に考え抜きます。考えることと、それを言語化して書き出すことで、思考を整理していくんです。先ほど感覚を信じるといいましたが、実際はかなり論理的に詰めていきます。これは前職で学んだことが活きているかもしれませんね。そうして積み重なってできた「勘」を信じているといったほうがいいかもしれません。
やり方は人それぞれだと思いますが、自分なりの「自分の信じ方」を見つけ出せれば、意思決定の軸はブレなくなると思いますよ。
<プロフィール>
大淵 亮平(おおぶち りょうへい)
1987年生まれ。京都大学を卒業後、ボストン・コンサルティング・グループに入社。大企業の経営コンサルや新規事業立ち上げの経験を積む。2011年に株式会社WACULに入社、取締役に就任し開発と営業以外の全てを担当した後、同社代表取締役CEOに就任。