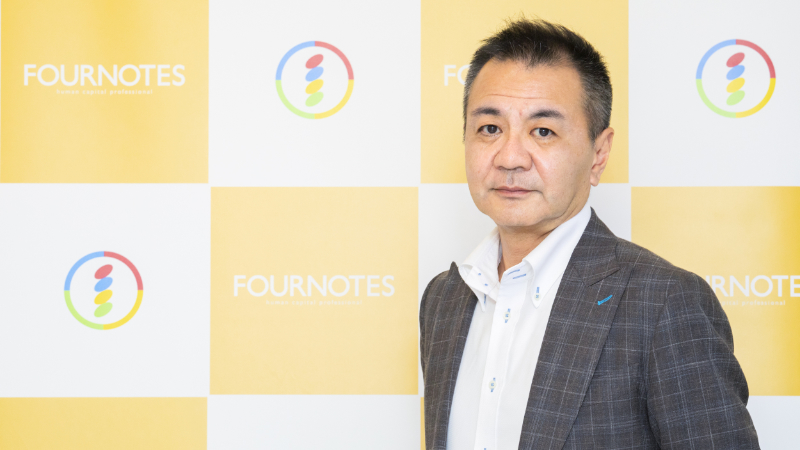化石資源から脱却、光合成由来のバイオテクノロジーでつくる地球環境とは?~ちとせグループ藤田朋宏氏

温室効果ガスを主因とする気候変動による世界的な災害の多発、農林水産、観光業などへの打撃等により、地球環境の持続性への意識は急激に高まりつつある。しかし、化石資源に依存せざるを得ない現代社会では、わかってはいるけれどやめられないという不本意な状態が続く。これに対して、ちとせグループでは化石資源を基点に構築されている産業構造を光合成基点に組み変え、循環型社会に近づけるための研究と事業を行っている。空から降り注ぐ太陽エネルギーから生まれる、生物の光合成由来資源は無限の潜在力を秘めているのだ。今回、どうすれば健全に資源シフトが成功するのか、千年先のビジョンを描くちとせグループ代表 藤田朋宏氏に話を聞いた。
産業構造に依存している地球環境づくり
-化石資源依存の状態をなかなか変えられない根本問題は何なのでしょうか?
現実的に化石資源の利用がなかなかやめられないのは、現代文明の基礎となっている産業構造自体が、化石資源を掘削して取り出したものの上に成り立っているからに他なりません。原油をクラッキングすることで、エチレン、プロピレンなどの化合物を得たり、重油、ガソリン、ジェットといった人の移動に資する燃料を生成したりするのです。つまり、こういった化成品によって成立している産業構造が土台になって世界の合理的な経済活動は成立しています。ある特定のテクノロジーのイノベーション、たとえば、バイオマスだけ切り取って環境に適応させるといったやり方では、コスト高になり到底経済合理性が成り立ちません。政府が補助金を入れて立ち上げたとしても、止めた瞬間に立ち行かなくなるのです。
そこで、ちとせグループでは同じ原料でできる化学品、医薬品、食品、農産物、エネルギーのうち、これとこれをいっしょに作れば、規模の拡大が可能となり経済合理性が成り立つという分野にターゲットに絞り、ゆくゆくそこを大きくしていく戦略を取っています。
我々はバイオテクノロジーの可能性を追求することで、埋蔵量に限りがある化石由来の資源からではなく、無尽蔵とも言える光合成由来のサステナブルな資源によって、新しい世界の経済社会を成り立たせようとしています。
21世紀初頭のテクノロジーでできることは限りがありますが、今タネを仕込んでおけば、50年後100年後に花開く分野は何なのか? 今は小さくてもいいから1000年という長期を見据えて、経済合理性が成り立つ部分から着手しているのです。
-御社の事業をもう少し具体的ご紹介お願いいたします。

我々の事業は、3つの技術分野から成り立っています。まずはじめに、独自の品種改良やゲノム編集などを活用し、産業上有用な能力を有する生き物を創り出す「創出」技術。次に、製造コストや環境負荷を下げながら安定的に生き物を増やす「培養」技術。そして最後に、観察とデータ解析から生き物の実際の動向を知る「把握」技術です。
ちとせグループでは、これらの技術群を活用し、様々な社会課題を解決するための事業を展開しています。ここから簡単に3つの事業を紹介します。
まず1つ目は、藻類タンパク質の世界的な普及を目指す事業。
2030年、タンパク質の需要と供給のバランスが崩れるというタンパク質危機が訪れると言われています。そこで、我々は大豆の約15倍ものタンパク質生産性を誇る藻類スピルリナを食のスタンダードにまで普及させることで、タンパク質危機の解決に貢献することを目指しています。ちとせ独自の、スピルリナを効率的に大量培養する技術、加工する技術により、無味無臭の生スピルリナを製品化。また、スピルリナをタンパク源として様々な食品に活用するための独自技術を開発し、技術を利用した製品化ならびに販売を行っています。
2つ目は、東南アジアの農業を環境持続型に変えることを目指す事業。
東南アジアの農業は、質より量を重視し、農薬や肥料を大量に使用する大量投入大量廃棄型の農業が蔓延しています。この農業で栽培された農作物は、安さを重視した低品質なものが多いのが現状です。我々はこの現状を変えるべく「ちとせ野菜」というブラントを立ち上げ、いちごやトマトなどをマレーシアの自社農園で生産し、シンガポールで販売を行っています。この活動を通じて、生産者側には高品質な農作物を栽培する環境配慮型農業を広げ、消費者側にはプレミアのついた農作物への理解を深めてもらうことを主導しています。ちとせ野菜は現在、シンガポール伊勢丹他、ミシュラン獲得レストランや人気洋菓子店、シンガポールを代表するリゾートホテルなどの有名店や、クアラルンプールでも販売中です。また、現地農家への技術移転も行いつつ、他の東南アジア諸国への農業プロジェクト拡大も計画しています。
3つ目は、スーパーセルで世界の抗体医薬品製造プロセスを塗り替えることを目指す事業。
世界では、再生医療のニーズやアンメットメディカル(治療法が見つかっていない疾患)へのニーズが日々増大しています。ちとせでは、そのようなグローバルヘルスケアに貢献すべく、ちとせ独自の圧倒的な生産性能を有するスーパーセルを活用することでバイオ医薬品製造プロセスを構築し、世界の抗体医薬品製造プロセスのスピードアップ及び低コスト化の実現を目指しています。
今はこうした事業が、11のグループ会社で役割分担しながら同時並行で進んでおり、その中でも調達金額が30億円以上必要な規模となっているものが4つ、5つと育ってきています。
ちとせ研究所の二度目の創業

-ネオ・モルガン研究所(現ちとせ研究所)に参画され、現ビジネスモデルの実質創業に至る経緯を教えてください
幼少のころから昆虫や魚や草木などさまざまな生き物を育て、個々の生き物の成長や集団としての関係や変化をじっと観察することが好きでした。子供ながらに未来の地球を考えた時、緑に溢れた循環型になっている必要があると考えていました。そこで、大学進学時は必然的に生物学系の学部を選び、遺伝学を専門とする研究室に入ったという経緯があります。
ところが、実際の研究活動は、ショウジョウバエの卵黄で見つかっている遺伝子をカイコで同定するというルーティンワークのようなものにすぎなかった。「あるに決まっているものを探すことが研究なんですか?」と、教授とよく議論したものです。あるに決まっているものは、見つけたい誰かが見つければいいじゃないかと考えていました。その延長に未来はないし、何も起きません。
そもそも生物に興味があったのは生命や人間社会が成り立つ大きな仕組み自体を知りたかったからなのです。そこで今度は、視点を変えてマクロ経済学など経済、経営の勉強をするようになりました。人間の社会がどのように成り立っているのかを追究しようと。
社会や経済はどのように成り立っているのか?は、結局企業経営の現場に入ってみないとわからないというのが結論でした。そこで外資系の経営コンサルティング会社を就職先として選ぶことにしたのです。
-コンサルタントから経営者になろうと思われたのは?
コンサルタントとしては主に組織戦略分野で、人事評価制度を作ったりしていました。制度の設計は当然にクライアントの要望に沿って作る必要があるわけです。しかし、自分がその評価制度で評価されて嬉しいかというと、必ずしもそうでもない。これではワークしないのではと疑問が出てきたのです。
そこで、結局自分で理想の経営を追求してみるしかないとの判断に至りました。そのためには自分の裁量で動かせる小さな会社でないと経営の真実はわからないなとも考えていました。
あるとき、学生時代に勉強していた進化遺伝子学の世界的大家である古澤満先生が、ネオ・モルガン研究所(ちとせ研究所の前身)を起業されていたことを知りました。あの古澤先生がやっている会社なら、是非話を聞いてみようとなったわけです。2000年当時はバイオベンチャーブームが起こり、我先にVCがバイオベンチャーに投資するという加熱した状態がありました。
その中の1社としてVCの誘いに乗って起業した古澤先生ですが、もとより経営に明るいはずもなく、そもそも社員達が古澤先生の言っていることを正確に理解しているようには見えない。私が古澤先生と意気投合したこともありますが、この会社に入ると自分の存在が役に立つ気がして、ネオ・モルガン研究所に入ることにしました。
さて、この第一次バイオベンチャーブームでは、名の通った学者に資金をつけてほとんどが失敗。ネオ・モルガン研究所も事業計画もないのに資金を集めてしまっていた。このままいくと間もなく資金は底をついてしまうという会社にわざわざ入社したというわけなのです。
-創業者の古澤先生はどんな方ですか?

純粋な本来の意味での「科学者」であり、天才です。視点がいつも新しく、話していて面白い方です。インパクトファクターを集めて論文を書いて評価されることを狙う職業学者と違い、他者から見える実績を残すことはまったく考えてない。進化とは何か?の答えを絶えず追い求められています。
-その後の会社はどうなったのでしょうか?
2008年が大きな節目でした。リーマンショックが起きてVCも大幅人員削減となり、VCの担当者の皆さんも従前はバイオベンチャー50社を数名で手分けして担当していたものが、50社を一人で担当するということに。そこで、投資先の9割を畳まざるを得ないという判断に至ったようです。
VCの担当者が言うには、「御社は企業価値ゼロだから、潰してもいいし、買い取ってもらってもいいです」と。そこで私が借金してVCから株を買い取り、代表になったということなのです。良く決断したねと周りからは言われましたが・・。
当時の台所事情は、大した売り上げがあるわけではないのに、経費が3億円もかかっており、残資金は1.5億円しかないという状況になっていた。そこで、研究者を15人だけ残して、再スタートすることに。
古澤先生に、私が微生物をやりますからと言うと「ワシはバイ菌がきらいじゃ。やりたいのならどうぞ」(我々が扱っているのは病原体のようなバイ菌ではないのですが)と。とはいえ微生物以外の事業はうまくいかず、私が担当して上手くいき始めていた微生物事業を核にして育て、何とか1年で黒字化して危機を脱することができたのです。
研究者の創造力を生み出すイノベーションのマネジメント

-バイオベンチャーのイノベーションについてはどう思われますか?
よく技術シーズがイノベーションを起こすといわれますが、現実には革新的な技術シーズで起こすイノベーションはほとんどないと思っています。むしろ、作りたい事業が先にあってその事業を成立させるために欠けている技術シーズを外から持ちこむことでイノベーションが生れることが多いと思うのです。化学、医療、食品、エネルギー等様々な業態で、このプロセスのここを切り出して変えたら良いのではと技術の可能性を提案することが、我々の役割なのだと考えています。
なぜ技術シーズドリブンだと難しいかというと、基礎研究レベルから全てを解明しながら進めようとすると、途方もなく巨額の資金が必要だからです。結局、すでに動いている事業のボトルネックを解消するというテクノロジーでなければ経済的合理性が成り立ちにくい。なので、まずは社会実装するという強い意志を持ち続けることが大事なのだと研究者には口酸っぱく言っています。
-御社の競争優位の源泉である研究者のマネジメントの特長は?
採用した人材には組織のどこかに、必ず役割があり居場所があるものです。組織の中のこの機能が足りないので、機能が空いているから採用して育てるではうまくいかないと考えています。
まず、研究者を採用するには、何かの課題に対して一生懸命な人柄だというのがポイントになります。なぜなら、もともと研究対象を決めて採用するわけではなく、「藻でたんぱく質を作るにはどうしたらよいか」といった誰も取り組んで来なかった研究課題を急に提示することもあるからです。それでも課題を解決するために燃えるというのが研究者であり、そういった研究開発魂を持つ方を採用するようにしています。
基本的に最初に課題におけるミッションを決めて、擦り合わせればあとは任せる。我々のような事業は組織化してタスクを明確にするということでは作り得ない。よって、研究者が全力でトライアンドエラーしているかどうかを見ています。ただ、その努力自体が正しいかどうかはすぐにはわからないので、評価軸も長くとっています。
研究者マインドからすると、仮にお金をもらってこいといえば研究者はそれをやります。目的は明確だが、道はわからないという状況が、研究者がいちばん燃える環境なのです。
こういったマネジメントは、俗人的ではなく社風として作ってきました。あるとき研究受託先の三井化学さんから「ちとせは何でそんなにうまくいっているの?」と聞かれたので、説明すると、うちでもやってみたいとなった。現在、オープンイノベーションプロジェクトとして、三井化学さんから研究者の出向を受け入れ立ち上げているのが「植物ルネサンス」と「ティラポニカ」の2社になります。
ちとせグループの展望と事業からの気づき

-ちとせの名に込められているお考えは?
“ちとせ(=千年)”には、長期的に光合成基点の社会形成に役立つテクノロジーを活用した「事業を」社会に残すことができればいいなという思いを込めています。我々が死んで何百年もたった後になってこれを始めたのは、実はちとせだったとわかるものを作りたいですね。
なぜ、ちとせグループというホールディング体制にしているのかというと、事業ごとに会社として分けて切り出して運用していけば、その中のいずれかの事業は生き残っていくのではないかと考えているからです。極めて進化学者的な発想なのだと思います。一つにすべてを賭けようとすると、結果的になにも残らない可能性が高い。なぜなら、環境の変化に適応し続けるのは不可能だからです。
事業を作りたいネタ自体は現時点でも無限と言っていい程あり、ただ事業化が上手くいきそうなタイミングを待っているだけです。
-この事業を展開されて気づかれたことは?
日本人だからこそできるイノベーションの発想があるということです。これは日本語という言語の特徴からくる文化的な背景が生きていると思います。日本語で会話すると、本質的な理由を曖昧にしたままでも、お互い分かった気になって、合意できたりすることもあるので前に進むことがあります。
例えば、日本酒は古来から作られていますが、なぜ麹菌や酵母の役割が詳細にわかるようになったのはせいぜい数十年前の事です。細かい味を決めている様々な菌の働きまでは未だに解明できていませんが、「似たような味の酒ができているんだからいいじゃないか」と、日本では前に進める。
ヨーロッパでも似たような価値観がありますが、米国では一つ一つのシステムが明快に解明されていないと、それらを組み合わせて前に進めることが許されない社会構造になっていると感じる事が多いです。これらの差って、考えている言語の構造の差に起因しているところが大きいと思うのです。
つまり、結論ありき、解明していることの組み合わせではない、発想のプロセスを重視するという日本語で考えるからこそできるイノベーションがあると私は信じています。これは人類の財産としても守るべきで、日本人1億人は世界にとっても重要な存在です。日本語が話せる我々には世界のイノベーションの一翼を担う使命があると思います。
今後の事業展開

-御社の拠点がアジアに展開されているのはなぜでしょうか?
そこは光合成の生産性に関係します。つまり赤道付近の方が生物を大量に安価に生産できるということですね。光合成事業には温度、水、CO2と土地が必要で、大袈裟に言うと赤道付近では植物が太陽を浴びて伸びている姿が目視できる気になってきます。日本国内の気候・環境で、必死に生産性を上げても多寡が知れている。ブルネイですと何もしなくても倍の勢いで伸びますからね。
-事業構想通りなのでしょうか?
基本的には構想通りに進んでいます。構想通りいっていないことは何かというと、本質的でないことに時間がかかることですね。スピルリナの事業でも資金調達までに1年かかってしまいました。個別で事業ごとにお金集めなければならないとすると、それだけで時間が取られてしまいます。また、先ほど申し上げたような、研究者のマネジメントの問題もあります。株主が、研究者のマネジメントを理解せずに、自分の会社の企業統治機構だけ押し付けると組織が止まってしまうこともある。資金調達金額とガバナンスのコントロールのバランスをどう取るかが課題です。
現状、すでにいくつもの事業がラボでの実験のフェーズが終わり、次に広さ1,000㎡の屋外で実証してみて成功するという段階に来ました。いくつかの事業が成立することが科学的に証明できているわけなので、あとは規模を拡大し、本格的に大規模に生産するフェーズにはいっています。
ただ、拡大するとなると、高価な化成品の生産でも20ha(200,000㎡)のプラントが必要で、それくらいの規模がないと採算に乗らない。現在稼働しているテストプラントの200倍の規模で、建設には30憶円以上が必要となる。
また、さらに安価な食料品や、燃料を生産しようとするともっと大きな規模のプラントが必要となります。
いちご、ミニトマトの農場は現在7エーカーの規模で運営していますが、すでに需要が多すぎて応えられない状態になっている。次は、もうひと山まるごとの面積を開発することが必要です。実際マレーシアの大手企業が山を貸してくれるといっていますが、ここにまた30億円以上が必要だったり。このようにすでに実証が終わって拡大しようという事業が4つ、5つと育ってきました。
これらを全て足すと、200憶円の資金が必要な段階となっています。一つ一つのプロジェクトごとに資金調達していると僕の時間がいくらあっても足りないので、ちとせが運営するファンドの形式で資金調達ができないかを真剣に検討中です。出資していただける方は大歓迎です(笑)。
<プロフィール>
藤田 朋宏(ふじた ともひろ)
ちとせグループ(CEO)
1973年生まれ。東京大学農学部、アクセンチュアを経て、ネオ・モルガン研究所(現ちとせ研究所)の経営を皮切りに、日本、マレーシア、シンガポール、ブルネイに合計11社のバイオベンチャーを設立。バイオベンチャー企業群 “ちとせグループ” としてグループ全体の経営の指揮を執る。バイオサイエンス博士。
ちとせグループ
https://chitose-bio.com/jp/
CHITOSE BIO EVOLUTION PTE. LTD.
株式会社ちとせ研究所
Chitose Agri Laboratory Sdn. Bhd.
株式会社日本バイオデータ
株式会社タベルモ
Chitose Agriculture Initiative Pte. Ltd.
株式会社フローラインデックス
株式会社ちとせバイオロジクス
株式会社植物ルネサンス
株式会社ティエラポニカ
等