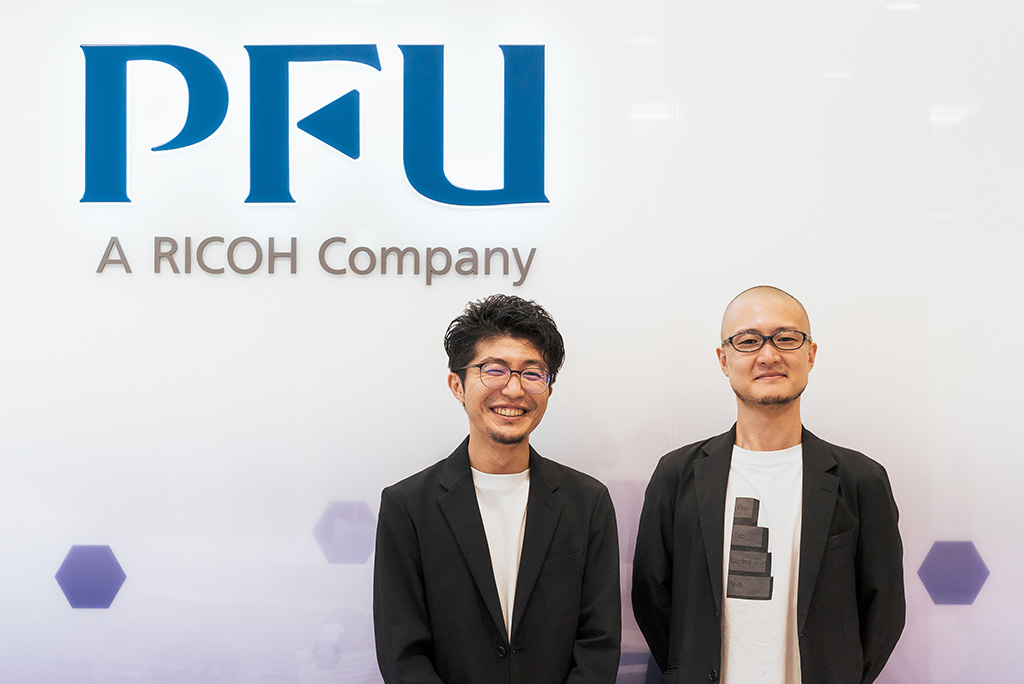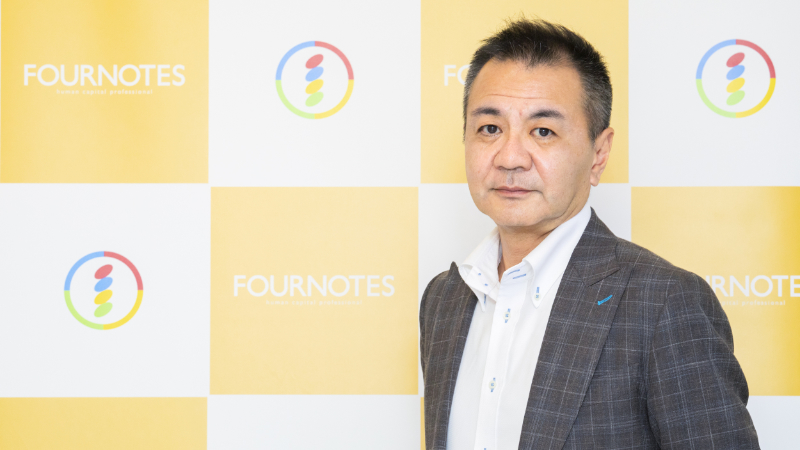「バックオフィスもメンバーの一員である」という認識が、管理部門のリモート化を促進させる――バックオフィス座談会


コロナ禍でリモートワーク化が推進される昨今。しかし、「バックオフィスは例外」という認識のもと、いまだ出社を余儀なくされている人員も少なくない。書類やデータのクラウド移行が可能になった現代において、バックオフィスのリモート化が進まない原因は何なのか。今回は、実際にバックオフィスで働くMさん(IT企業)、Yさん(アパレル企業)、Iさん(コンサル企業)の3名に、現在の勤務状況や日々感じている課題について語ってもらった。
【参加者プロフィール】
・Mさん
IT系企業の業務管理部所属。シェアード化でグループ会社のバックオフィス業務の集約に取り組む。経理Gでグループ会社の決算を担当。現在もフル出勤中。
・Yさん
アパレル企業の経理部所属。主に子会社の月次業務から決算までと、店舗等の家賃一括支払いなどを担当。オフィスには週1~2日ほど出勤。
・Iさん
外資系コンサルティング企業・法務部所属。現在はフルリモート中。
「コストセンター」と呼ばれてしまうバックオフィス
――まずは、普段の業務内容についてお聞かせください。
Mさん:私は、シェアードサービスセンターという、グループ会社や企業内のバックオフィスをひとつに集約化する部門で働いています。DX化、RPA(※)化の推進も担当しています。新卒から経理で働き始め、出産により休職・転職はしたものの、バックオフィス歴は15年になります。
※RPA:Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)の略。ロボットを利用して業務の自動化や効率化を図る取り組みを指す。
Yさん:アパレル製造・小売業の会社で経理をしています。子会社がいくつかあり、その決算から日々の業務まで見ています。新卒で社員カメラマンとして就職し、その後いまの会社に転職。もともとはウェブサイトの制作や撮影をする部署にいましたが、2年目に経理部へ異動となり、11年が経ちました。
Iさん:いまはコンサル会社で法務の仕事をしていますが、以前はIT系のテクノロジーサポートの会社で経理や人事、契約などさまざまな仕事をしていました。
法学部卒で公務員志望だったんですが、就活当時すでに社会人だった家族からIT業界に入ることを強く勧められまして。その後、留学や出産を通して、最終的に「やはり法律に携わりたい」ということに気づき、法務の仕事に就いてから今年で15年になります。
――皆さんさまざまな背景がありますが、実際にバックオフィスとして働くことの印象はいかがでしたか。
Mさん:仕事がいい意味で「自己完結型」なところが気に入っていますね。自分の業務を自分の裁量でできるのがいいな、と。
Yさん:たしかに。私は新卒で4年間カメラマンをしていて、クリエイティブな仕事特有の「正解がない」という側面が楽しくもつらい部分だったんです。一方、経理という仕事には意外とクリエイティブな側面があり、加えて必ず「正解」も見つけることができる。それがやりがいにつながっています。パズルに取り組んでいるイメージですね。
Iさん:「管理部門にもクリエティブな部分がある」というのはよくわかります。私が面白味を感じているのも、まさにそういうところ。法務部は依頼されて契約書を作ったり、問題が起こった際に社員が相談に来たりと、受け身の印象が強いですよね。
でも、自分から会議に参加して、「このプロジェクトには、こういう契約の仕方がいいですね」とか「こういう点でリスクが出てきそうです」と前のめりに提案していくこともできる。経験を生かして、問題が起こる前にリスクヘッジしていくような動き方をすると、非常に重宝される仕事だと思っています。
Mさん:管理部門も、自分から提案することが求められる時代ですよね。これはコロナ禍以前から変わりませんが、やっぱりバックオフィスって「コストセンター」という印象が強いじゃないですか。「稼がないからコストを削減しないといけない」みたいなプレッシャーが常にのしかかってくる。

Yさん:うちの会社も正直なところ、売り上げ重視的な意識が大きいので、売り上げを生まないバックオフィスは評価されづらい立ち位置にありますね……。
Iさん:バックオフィスを定量的に評価すること自体が難しいですよね。私はマネジメント側の立場ですが、チームメンバーと目標設定をするときは、「難易度の高いプロジェクトでどんな関わり方をしたか」「どのようなリスクを検知してどう働きかけをしたか」といった部分で、ビジネス面からもフィードバックをもらえるような評価システムを構築しています。
Mさん:「バックオフィスは、与えられた仕事をただやっていればいい」という時代もたしかにありましたが、今はそうではなくなりつつありますね。ただ、旧態依然とした考え方の人がいまだに多い分、難しい側面もある。
Iさん:管理部門でも、「いかに費用対効果を意識して、他部署がビジネスに集中できるような環境を提供できるか」を積極的に考えることが求められています。むしろそうしていかないと、いつかバックオフィスはAIやロボットに取って代わられてしまう。今はその転換期なのかもしれません。
コロナ禍によって顕著になった“三社三様”の働き方
――コロナ禍によって、バックオフィスの働き方はどのように変化しましたか。
Mさん:実は、うちはずっと変わらずフル出社をしていて……。リモートワークにまったく移行できていないんですよ。
Yさん:ええ! そうなんですか。
Mさん:システム開発部門などは、昨年からフルリモートに移行しています。バックオフィス部門はかなり保守的で、監査面でも意識が高いのか、セキュリティ・インシデントに対する警戒感も強い。そうした社風ゆえに、バックオフィスのリモート化に時間がかかっています。
Iさん:なるほど、たしかに社風は影響しますよね。
Mさん:はい。50社ほどのグループ会社の中には、社長の一存で一気にフルリモートを実現できている企業もあります。そういう姿を見ていると、コロナ以前からリモートに着手する準備ができていた企業が一気に舵を切って、反対に準備をしていなかった会社は間に合わなかったんだな、ということがわかります。
Iさん:私の会社には、コロナ以前からリモートワークの制度がありました。個人的にはオフィスのほうが仕事がしやすかったので出社を選んでいましたが、コロナ禍になってからは、「どうしても出社が必要な人以外は基本的に全面リモートで、オフィスに行くのであれば申請が必要」というルールに変わりました。ですから、現在は全面的にリモートです。
Yさん:うちも、割とすぐにリモートに移行しました。ただ、どうしても出社しなければならないこともあって……。やっぱり紙ベースの業務ばかりなんですよね。送られてくるものが紙だから、それを取りに行かないといけない。そのために、今も週1〜2回の出社がベースになっています。

Mさん:紙ベースの業務がリモート化を阻んでいるというのは、すごくよくわかります。うちも請求書の“原本主義”がすごく強くて。PDFで保存しても問題はないはずなんですが、データで送られた請求書をわざわざ紙で印刷して保管する、みたいな謎の作業をいまだにしています。
Yさん:わかります(笑)。私はリモートになってから、請求書のために出社するのが面倒だったので、自主的に取引先に「データでください」とお願いしています。ただ、メールで受け取っても、「税務調査が入ったときに困るから」という理由で、わざわざ紙ベースでも会社に送ってもらっているという……。
Mさん:取引先のやり方にも合わせないといけないところがあるから、難しいですよね。
Iさん:うちもやはり、取引先によって変わってきます。電子印は社内では認められているんですが、お客様に「電子印は信用できない」と言われてしまえばそれまで。ただ、コロナ禍によって少し潮目は変わってきている気がします。
契約書はさすがにハードルが高いけれど、業務の取り決めをするような書類までは電子捺印でもいい、という取引先も増えています。そのあたりは柔軟になってきているのかな、と。
Mさん:それはいい傾向ですよね。
Iさん:ただ、法務部としては担当者レベルで合意形成をなされてしまうと困ることも出てくるんですよね。いざ蓋を開けてみたら、決済権限を持っている人の承認が得られていなかった、といったアクシデントが出てきてしまうかもしれないので。
あまり緩すぎるのもよくないと思っています。いかに時代に即した新たなルール作りができるかが求められている気がしますね。
使用ツールの乱立が引き起こす問題
Iさん:経営陣の人たちにとって、現場で具体的に「何が起こりそうか」「何が起きているのか」は見えづらいので、管理部門としては、経営陣が舵を切るための提案や働きかけは必要だなと思います。「よくわからないけど、現場が回ってるならこのままでいいか」と見過ごされるケースって、よくあるじゃないですか。
Mさん:ありますね(苦笑)。
Iさん:たとえば悩ましいのがツール問題。各部門で使っているツールが別々で連携されておらず、手入力が発生するためにミスも起きるし、工数もコストもかかる。本来であればそういった課題を経営層が現場から吸い上げるべきなんだけど、やっぱり経営層からは課題が見えづらいのが現実で。
――「ツールが乱立している」という課題については、よく耳にします。
Mさん:システムの統合に関しては、いままさに私が担当している業務ですが、本当に難しいですよ。たとえば、私は固定資産を担当しているんですけど、固定資産に対する考え方も処理の仕方も部署によってまったく違う。
Yさん:各社で規格が違うから、ツールをそのまま乗り換えることって難しいんですよね。
Mさん:そうなんです。グループ会社が使っていたツールを強制的にやめさせて、ひとつの共通のシステムに統合したんです。でも、各社で使われていたツールとの仕様があまりに違いすぎて、すごく大雑把なシステムしか作ることができなかった。最大公約数しか拾えない、というか。
結局、各社から「無理です、使えません」といった苦情が殺到。正直、長期的に利用することは難しいのかもしれませんね……。
管理部門が時代に合わせて変化していくために必要なこと
Iさん:会社がさまざまな新しいシステムを導入し、「これ、すごく便利だから使ってみて」と押し付けられることもよくあって(苦笑)。導入した人たちの思い入れもあるので、うまくまわらなくても結果いろんなシステムが乱立したまま残ってしまうという課題がありますね。
「やってみよう精神」のよくない面が出ているというか。日頃お客様の課題を解決しているコンサル会社なのに、社内になると途端にダメになるなあ、と。
Mさん:すごくわかります。「社内になるとダメ」なんですよね(笑)。うちの会社も、まさに顧客にシステムを提案する会社のはずなのに、社内ではうまくいっていない。
Yさん:うちの会社は保守的な側面もあるんですが、今後いろいろなシステムを取り入れて、できる限りリモートを続けていこうという姿勢なんです。そこで最近コンサルを入れて会計システムを入れ直したのですが、そのおかげで滞りなく切り替えができたんですよね。
――外部からのサポートによって、システムが合理化された、と。

Yさん:そうですね、ある種の“強制力”をもって合理化していく、みたいな。
Iさん:「だからコンサル会社が儲かるんだな」って、いま改めて実感しています(苦笑)。
Yさん:あとは、やっぱり上層部の意識改革ですかね。最近うちの経理部ではマネジメントクラスが世代交代をして、若がえりしたんです。その方は新しいシステムを積極的に取り入れていきたいタイプなので、これからちょっと社内の空気も変わるかなと思っています。
Mさん:権限をもっている人たちが動かなければ、結局は現場の声も吸い上げられないですよね。うちの上司は、「リモートワークを推進したら、みんな仕事しなくなっちゃうでしょ」って本気で言っちゃうタイプなので、本当にキツイですよ。
Yさん:それはもう、真面目に転職も視野に入れたほうがいいかもしれないですね……。
Iさん:私自身は、バックオフィスもチームのメンバーであるわけだから、もっと積極的にビジネスに介入していくべきだし、提案型になっていくべきだと思うんです。ただ、その声を聞いてくれる経営陣がいない限り、実際には難しいかもしれませんね。
著名な経営者が書いたビジネス書を読んでいると、「管理部門も含めてのチームだ」と語っているケースがとても多いと感じます。社風がそうであれば、バックオフィスのメンバーもずっと働きやすくなるでしょうし、より時代にフィットした働き方を提案したり選択したりできるようになるはず。そういう社風作りが、コロナ禍のいまこそ求められているような気がしますね。
(執筆:園田菜々 編集:波多野友子/ノオト)