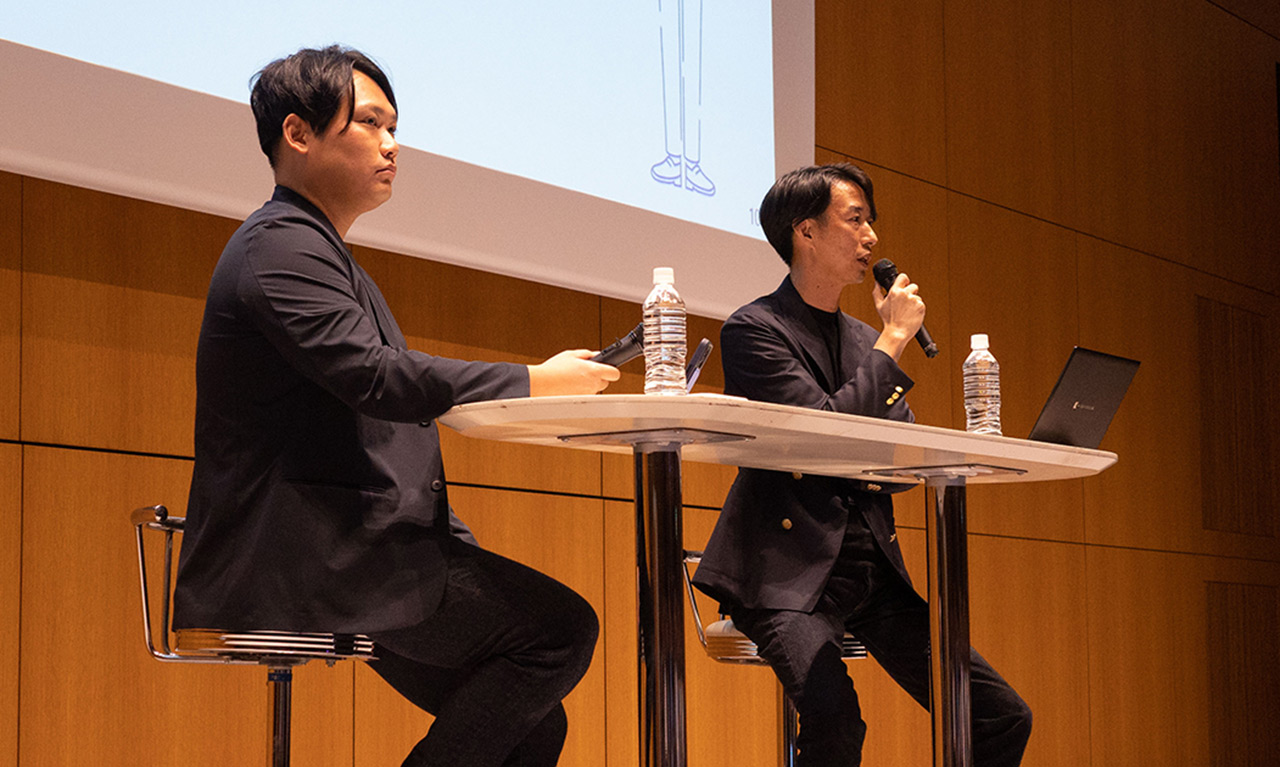従業員を雇用したら行わなければならない社会保険や給与関係の手続きまとめ


従業員の入退社にともなって発生するのが各種手続きです。
転職が珍しくない今の時代は、通年でこの手続きを行なっている会社もあることでしょう。
今回は、入退社のときに会社が行う手続きについて解説していきます。
入社手続き
労働条件を書面で明示
どのような雇用形態であったとしても、従業員を雇用したら労働条件を明示しなければならないことが労働基準法で定められています。特に重要なのは以下の項目です。
・労働契約の雇用期間に関すること
・就業場所や従事する業務
・始業・終業時刻、休憩、残業、休日、休暇などに関すること
・給料や給料の支払日、支払方法など
・退職に関すること
書面の形式や名称は自由に決めることができますが、上記の項目については必ず明記しておかなければなりません。
厚生年金保険と健康保険
最初に行うべき手続きは社会保険の手続きです。厚生年金保険と健康保険は従業員だけでなくその家族にも関係している重要な手続きなので、できるだけ早くに手続きを行うようにしましょう。
手続きを行う際は、原則として雇用から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を作成し、事務センターに郵送するか年金事務所の窓口に持参するかのいずれかの方法で書類を提出します。
2018年3月からは、「マイナンバー」を記載することで年金番号や本人の住所などを記載する必要がなくなりました。
パートの場合は、労働時間と労働日数がフルタイム4分の3を超えると加入義務が発生します。
雇用保険
雇用保険の加入義務は、厚生年金保険や健康保険とは条件が異なっており、1週間の所定労働時間が20時間に満たない人や学生の加入義務はありません。
入社手続きを行う人が加入対象となる人であれば、原則として雇用した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。
書類の作成には年金・健康保険の手続きと同様にマイナンバーの記載が必要です。
所得税の手続き
所得税の手続きに必要なのは「給与所得者の扶養申告等(異動)申告書」です。
副業を持っている従業員が他の会社で給与を受け取っている場合にはこの手続きは不要で、転職者は前職で受け取った源泉徴収票が必要です。
“給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除などの諸控除を受けるために行う手続です。なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。”
<引用元>国税庁:[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
住民税の手続き
住民税には、個人で納付する「普通徴収」と企業が源泉徴収して納付する「特別徴収」という納付方法があります。
源泉徴収を行う会社は、従業員が住民登録している自治体に「給与所得者異動届出書」を提出します。
1月から5月までに前職を退職している人の住民税は、前職を退職するときに一括徴収されています。
入社時に従業員が提出する書類
・マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードやマイナンバー入り住民票と写真つき身分証明書など)
・雇用保険被保険者番号が確認できる書類(雇用保険被保険者証など)
・扶養控除申告書
・給与振込用の銀行口座を確認できる書類
・現住所を証明する書類
・前職の源泉徴収票と住民税の異動届出書
退職手続き
厚生年金保険と健康保険
退職したらまず行わなければならないのが、厚生年金保険と健康保険の資格喪失手続きと保険証の回収です。
退職から5日以内に、加入時と同じく郵送か直接窓口へ行って「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」と「保険証」を提出します。
給与から差し引かれる保険料は資格喪失日の前月分までです。
雇用保険
雇用保険の手続きは、退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。
企業には離職票の交付義務があるため、退職者が離職票を希望する場合には離職票を作成します。
所得税の手続き
退職者のための年末調整は原則として不要ですが、最後の給与明細と一緒にその年の1月1日から退職日までに支払った給与分の源泉徴収票を発行します。
12月に給与の支払いを受けて退職する人や心身の障害が理由で退職し再就職が望めない人、死亡した人については年末調整を行う必要があります。
“年末調整は基本的に各年の最後の給与を支払う際に行うこととなっており、年の途中で退職した人の年末調整はできないこととされています。しかし、すべての退職者が年末調整の対象者にならないわけではありません。今回はその例を紹介していきます。”
<引用元>経営ハッカー:退職者のうち年末調整の対象になる5つの項目と注意点まとめ
住民税の手続き
住民税の特別徴収を行なっていた場合は、退職者が住民登録をしている自治体に「給与所得者異動届出書」を提出します。
退職者が住民税を支払う自治体が引っ越しにより変更されるなどの事情によっては、2つの自治体に届出書を提出しなければならない場合があります。
退職金の控除計算
退職金が発生する場合は、退職金の源泉徴収が必要です。
この場合、給与の源泉徴収票とは別に退職金の源泉徴収票を退職者に渡すことになります。
退職時に従業員が提出するもの
・保険証
・退職届
・返却の必要がある備品等
まとめ
入退職手続きは、基本的に同じ項目を同じ順番で処理していくイメージです。
それぞれの書類に提出期限が設けられているので、退職手続きを開始するタイミングになったら速やかに行いましょう。