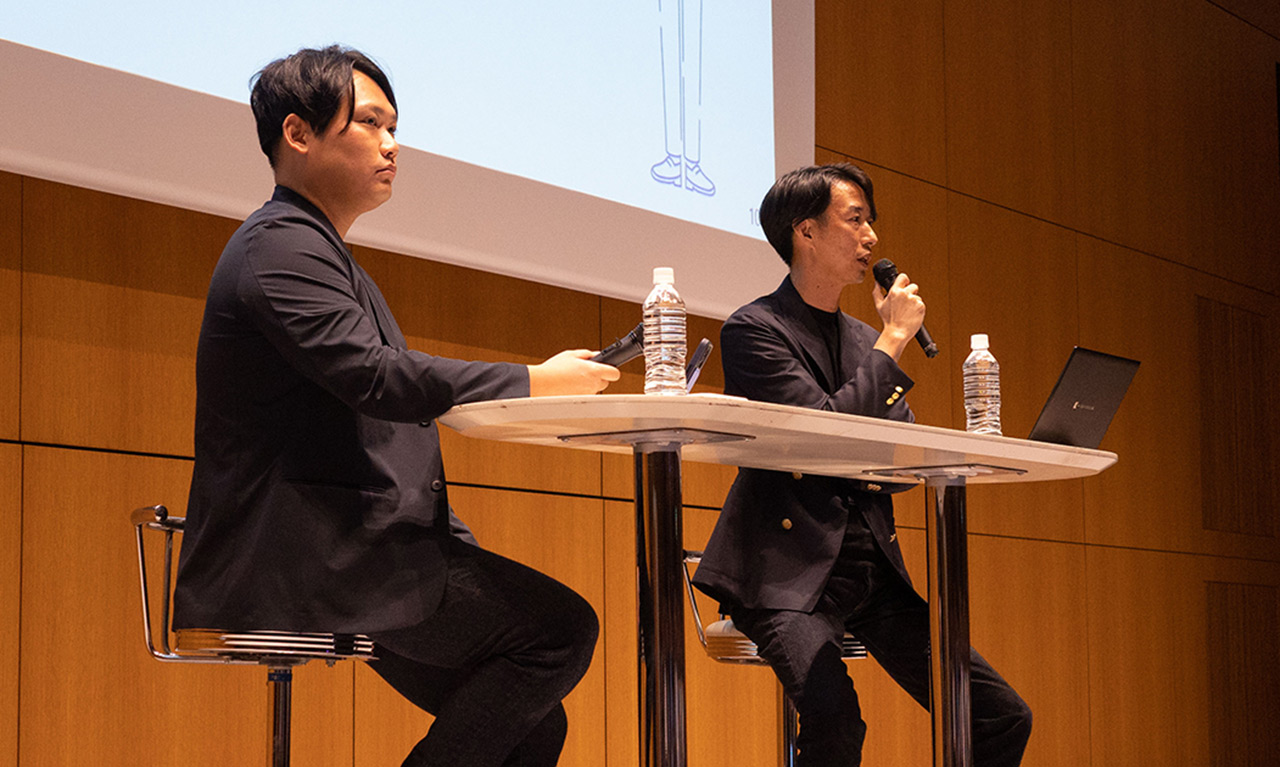みなし労働時間制は働く人々の福音なのか?それとも悪夢なのか?

みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわらず、決められた労働時間分働いたものとしてみなす制度です。みなし労働の対象になる業務については、労働基準法で定められており、どんな職種の人でも対象になるというわけではありません。

みなし労働制は、労働者にとってプラスかマイナスか。今回は、このみなし労働制について詳しく見ていきましょう。
みなし労働の対象となる業務は決められている
現行の労働基準法において、みなし労働時間制は、以下の3種類が定められています。
1. 事業場外労働(第38条の2) 例えば、外回りの営業職や海外旅行の添乗員など、労働時間の把握が難しい場合について適用されます。例えば営業職の場合、朝客先に直行し、午後3時にオフィスに戻ってきたとします。このケースでは、午後3時までをみなし労働とし、それ以降の退勤するまでの時間を労働時間として取り扱います。ただし、以下の場合ではみなし労働とされない可能性があります。
・事業場外労働のグループに労働時間の管理をするリーダーがいる場合 ・携帯電話などで、外出先にいても随時指示を受けながら労働する場合 ・訪問先と帰社時刻など、具体的な指示通りに当日の業務を終え、オフィスに戻る場合
昨今、日本企業でも導入が進んでいる在宅勤務については、以下の条件を満たせばみなし労働となります。
・寝食を含む私生活を営む自宅で業務が行われている ・情報通信機器が、常時通信可能な状態におくと指示されていない ・使用者の具体的な指示に基づいて、随時業務が行われていない
2. 専門業務型裁量労働制(第38条の3) 研究開発など、高度な専門性をもって業務にあたる従業員を対象とした区分です。対象となる業務は以下の通り定められています。
・新商品、新技術の研究開発業務 ・情報システムの分析、設計業務 ・取材、編集 ・デザイナー ・プロデューサー、ディレクター ・厚生労働大臣の指定する業務 ・コピーライター ・システムコンサルタント ・インテリアコーディネーター ・ゲーム用ソフトウェア制作 ・証券アナリスト ・金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発業務 ・大学での教授研究 ・公認会計士 ・弁護士 ・建築士 ・不動産鑑定士 ・弁理士 ・税理士 ・中小企業診断士
専門業務型裁量労働の導入にあたっては、労使協定の締結、届出が必要です。自社の業務が該当するかどうか知りたい場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
3.企画業務型裁量労働制(第38条の4) 事業の運営に関して、企画、立案、調査及び分析の業務を行う従業員に適用される区分です。2000年の改正で新たに追加され、主にホワイトカラーへの適用を想定しているといわれますが、単なる事務職などは含まれず、ホワイトカラーの全てに適用されるわけではありません。
みなし労働で勘違いしやすいポイント
みなし労働を導入すれば、実際の勤務時間が10時間であっても8時間分のみなし労働とできるので、人件費を抑えられると思うかもしれません。勘違いされやすいポイントですが、みなし労働でも実際の労働時間が10時間というように、法律で定められた労働時間を超える場合には、36.協定を結ばなくてはいけません。
また、みなし労働であっても、深夜・休日労働、時間外労働については割増賃金を支払わなくてはいけません。さらに休日出勤した場合も、みなしで8時間分の勤務をしたとして、休日手当が支給されます。
「労働時間の把握」が可能かどうかが争点に
実際、みなし労働の対象者ではない従業員までみなし労働とし、所定の賃金を支払わないブラック企業も存在します。こうしたケースでは、みなし労働に当たるかどうかを巡って、従業員と裁判になるケースもあります。
ある企業では、外回りの多い営業職の社員をみなし労働性3パターンのうち「事業所外労働」に当たるとしてみなし勤務としていたため、月80時間の残業をしていたにも関わらず適切な残業代が支払われなかったとして、従業員が会社側を相手取り、裁判を起こしました。
ここで争点となったのが、「2.携帯電話などで、外出先にいても随時指示を受けながら労働する場合」にあたるかどうかです。対象社員は営業用の携帯電話を会社から支給されており、いつでも連絡がとれる状態となっていました。このように、事業所外でも頻繁に上司と連絡をとっていたことで、「労働時間の把握が難しい」とは判断しにくいといえます。
法律ができた当初は、外回りの営業マンなどを対象者として想定していたと考えられますが、昨今は携帯電話でいつでも指示や連絡ができるので、「労働時間の把握ができない」という状況はかなり限定的になってきているといえます。
「みなし残業」は法律で決められていない
企業の中には、あらかじめ残業代を固定で決めておき、一律で支給するという企業もあります。「みなし残業代」と言うこともありますが、こうした用語は実は法律では定められていません。
みなし残業代を導入すると、雇用側は給与の支払い業務がシンプルになりますし、従業員側は早く業務を終わらせても一定の残業代が支払われるので、業務効率を高めようというモチベーションがわきます。
また、「だらだらと仕事をしている人のほうが残業代を多くもらえる」という不公平感も抑えられます。しかし実際のところは、「残業代はすでにみなしで支払っている」という事実を盾に、超過労働をした場合でも適切に残業代を支払わない企業が多く存在します。また、従業員側も泣き寝入りというパターンが多いようです。
「みなし残業代」を導入する場合は、就業規則に何時間分の残業代にあたるのかをあらかじめ明記し、それを超過する分の残業代については、所定の割増賃金を支払わなくてはいけません。この「みなし残業代」も裁判になりやすいのですが、この通常の賃金と割増になるべき賃金がしっかりと区別されているかどうかが争点となります。
「みなし労働」の条件を知っておこう
「みなし労働」だからといって、まったく出勤しなくてよい、または残業代や深夜手当などを支払わなくてよいということではありません。労使間でのトラブルを防ぎ、自らの身を守るためにも、「みなし労働」についての対象業務や法で決められた労働条件などは知っておくべきでしょう。