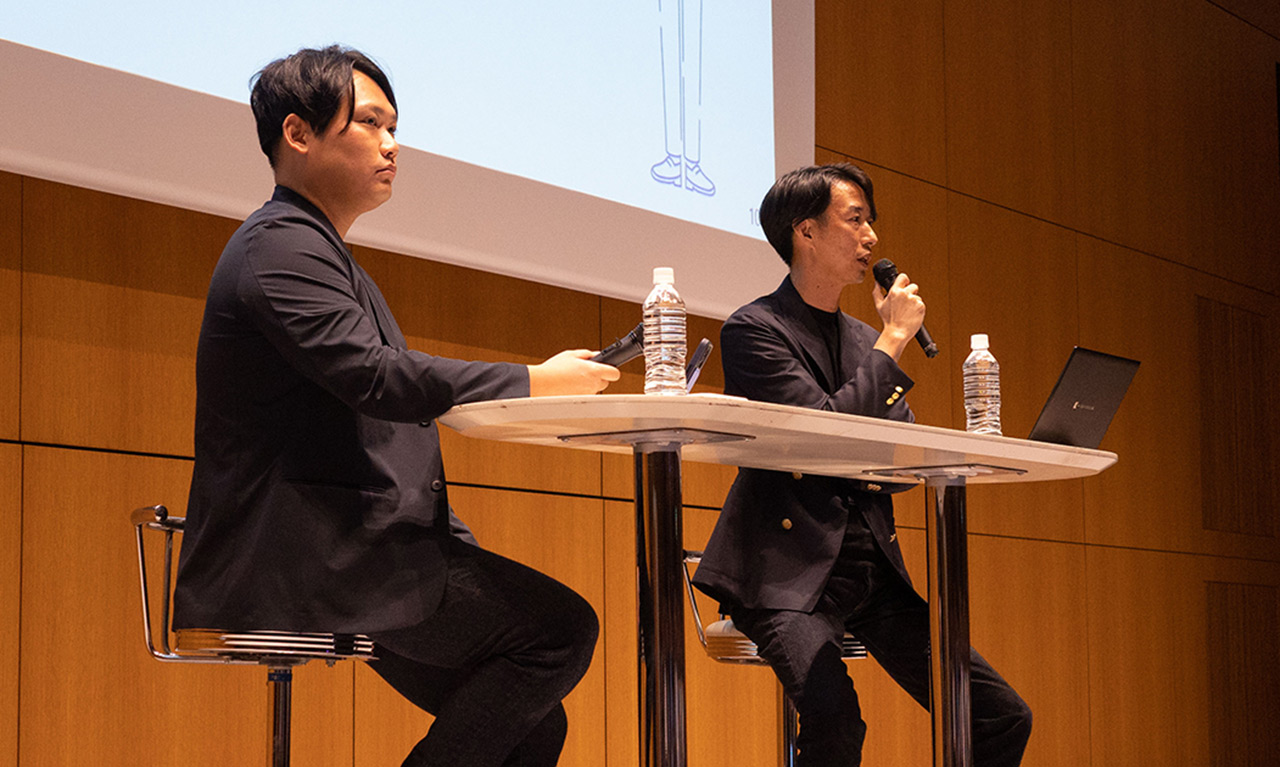国外への税金逃れが禁止に。7月1日から施行される「国外転出時課税制度」を徹底解説


「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」が2015年7月1日より適用されることとなりました。本来日本の税金は日本の居住者(住民)にしか課されません。
したがって、含み益をもった(値上がりした)株式などを持っている居住者が香港のようにキャピタルゲイン(値上がり益)に課税しない国に移住して、非居住者になって売却等で処分すれば全く税金がかかりませんでした。このような制度ができた背景には、このような税金逃れ(租税回避)が横行したことがあります。
ただ、国外転出時課税制度は本人の租税回避の意思の有無に関係なく、海外転勤の際など様々なケースに適用されることがあるので要注意です。例えばオーナー社長の自社株を持っている息子さんが海外赴任した際、その持ち株の時価が1億円以上と算定されれば対象となるわけです。
1)国外転出時課税制度の概要
国外転出時課税制度は、海外移住をする際に含み益がある有価証券等に日本の税金が課税される制度です。以下もう少し詳しく見ていきましょう。
1. いつから適用されるのか?
平成27年7月1日以後の国外転出に適用されます。
2. 誰に適用されるのか?
時価の合計1億円以上の有価証券等を持ち国外に転出する人で、かつその転出前10年間で日本に住んでいた期間が合計5年以上の人が対象となります。日本国籍の有無は関係ありません。また出張などは一般的に対象外となります。
3. 課税対象となる「有価証券等」とは?
株式(上場・非上場に限らず)公社債、投資信託、ストックオプション、未決済の信用取引などのこと。未決済の信用取引などは損益を通算(相殺)して合計します。逆に不動産、預貯金、生命保険などは対象になりません。
4. 計算方法は?
納税管理人を選任するかどうかで異なります。納税管理人とは国外に転出すると税務署とのやり取りや申告などが難しいので代わって行う人です。別に資格要件があるわけでなく親戚などにも頼めますが国際税務に強い税理士などを頼む場合も多いようです。
納税管理人が選任されている際は転出日の時価で決済されたと仮定してその他の所得と一緒に申告計算をします。選任されていないときは転出予定日の3か月前の時価で同様に計算します。
5. 申告・納付期限は?
納税管理人を選任していない場合は出国の際までにしなければなりませんが、納税管理人を選任している場合は翌年3月15日までが期限となります。
2)「課税の取り消し」と「納税猶予」の制度
この制度によって、まだ株などを売却もしていないのに税金を納めなければならないことに困惑する人も多いのではないでしょうか?特に前に挙げた非上場の自社株を持っていて対象になってしまった方などは売却の予定がない場合も多く、そもそも現金がないため税金が払えないかもしれません。そこであるのが「課税の取り消し制度」と「納税猶予」です。
1. 課税の取り消し
まれに雑誌などで「5年以内に帰国する人には国外転出時課税制度は適用されない」という記事を見ますが、厳密にはそれは誤り。転出の日から5年以内に帰国した人は、帰国から4か月以内に税務署に更正の請求をすることで実質的に税金は返還されます。
したがって、5年以内に帰国の予定があっても申告・納税は(納税猶予の場合除き)必要となります。また、ここの場合の「帰国」は一時帰国ではなく日本に住居を定めるなど居住者になることをいいます。
その他、該当する有価証券等を5年以内に売却、贈与等した場合も同様です。
2. 納税猶予制度
「納税猶予制度」とは以下の手続きを行えば、課税対象になった人でも5年間(最長10年間)納税が猶予される制度です。
1. 納税管理人の届け出 2. 納める税金分の担保の提供 3. 確定申告書に納税猶予を受けようとする旨を記載 4. 継続適用届出書を提出
納税猶予制度によって、転出の日から5年以内に期限の延長の届を出すことで、猶予期間を最長10年まで延長することが可能。ただし、継続適用届出書は毎年3月15日までに前年12月31日現在の有価証券等の所有の状況を届けなくてはいけません。これを忘れると猶予は取り消されて課税されるので、注意が必要です。
3)「課税の取り消し」と「納税猶予制度」のメリット、デメリット
それではいざ自分がこの制度の対象の該当者になった場合、どちらを選ぶべきなのでしょうか。 一般的には「納税猶予制度」をお勧めしますが、以下でそのメリット、デメリットを見ていきたいと思います
1. 納税猶予制度のメリット
・滞在が長引いた際延長ができる 例えば帰国後更正で納税額を返却しようと思っていたところ、帰国が長引き海外駐在が5年を超えてしまった場合。更正はできず、いったん払った税金は戻ってきません。一方猶予の場合5年を過ぎて滞在が長引くことがわかっていれば、猶予を上限10年まで延長させることができます。
・実際に売却した際、売却額が申告額より低い場合救済措置がある 実際に株式等を売却した時の売価が申告時の時価より低い場合、猶予分の申告書を更正することにより実質的には猶予分の納税はその分だけ免除されます(ただし譲渡益にかかる所得税分の利子税は払う)。一方一旦納税した場合は、このような救済措置はありません。
2. 納税猶予制度のデメリット
・担保を提供しなければならない 所得税額に相当する額の担保を提供しなくてはなりません。担保は国債・地方債・税務署長が認めた有価証券・土地建物などです。手間がかかることは確かです
・猶予期間経過後や途中で売却した場合金利を払わねばならない 本税プラス猶予経過時、または売却時までの金利を払わなくてはなりません
・続適用届を毎年出さなくてはならない 上にも書きましたが、継続適用届出書は毎年3月15日までに、前年12月31日現在の有価証券等の所有の状況を届けなくてはなりません。これを忘れると猶予は取り消されて課税されるので注意が必要です。
4)まとめ
「国外転出時課税制度」は基本的に金融資産を多額に所有している富裕者層向けの制度なので、一般的にはあまり神経質になる必要はありません。また、海外への移住が一時的である場合、実質的に納税はしなくてよい制度(納税猶予または更正による還付)もあります。
ただ、国外財産調書制度(5000万円以上の海外資産を所有している場合の報告制度)など国境をまたいだ節税に対する税務当局の目は厳しくなりつつあるということは頭に入れていただいた方が良いかと思います。
この記事は、川井公認会計士税理士事務所 川井 隆史様に寄稿いただきました。 経営ハッカーでは、記事制作にご協力いただける方を募集しております。 お申し込みはこちらから